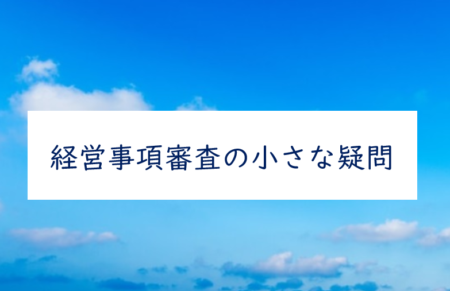「専任技術者」が1人しかいない場合のデメリット
おはようございます。
兵庫県姫路市の行政書士の秋田です。
暑いですね~
毎日、太陽ギラギラしすぎじゃありませんか?
外に出ると日焼けするというよりもフライパンの上で炙られているような気さえします。
今年の7月は8月の暑さ、8月はもちろん8月の暑さ、そして9月も8月の暑さとなる見込みだそうです。8月が3カ月続くなんて。
もう夏休みを増やしてもらわないといけませんね。

毎日暑いニャ~
水分補給、忘れないでね
さて、事務所雑感をご無沙汰してしまいました。
私は、建設業許可と産廃業許可をメインにお仕事をさせていただいておりますが、建設業の入力業務が続いておりました。
決算変更届は溜めないように致しましょう。といっても溜めてしまった場合は、ぜひ弊所で。笑
ちょっと気になる点がありましたので、まとめてみました。
専任技術者が1人しかいない場合のデメリットについてです。
ご存じのとおり、建設業許可では、必ず「専任技術者」という地位を有する人を置く必要があります。
専任技術者は、建設業の中の取得したい業種に関するプロ中のプロといったイメージです。この人がいるからこの業種は任せられるという資格です。
専任技術者になるには、国家資格などの資格を取るか、実務経験を1業種につき10年積んで、その地位に就くことができます。そして建設業許可を受けた営業所ごとに配置され、契約の適正な締結や履行を確保する役割を担います。
では、実際に現場に出て工事を監督するのは誰か、というと、専任技術者ではありません。
こちらは、「工事経歴書」の中にでてくる配置技術者に該当します。配置技術者は、施工現場に配置され、工事の技術的な管理を行う技術者です。主任技術者と監理技術者の2種類があります。
呼び方は様々ですが「現場監督」や「工事主任者」などがいらっしゃると思います。これらの方が配置技術者に該当しますが、原則として、専任技術者と配置技術者は兼任できません。
専任技術者は営業所に常勤し、配置技術者は工事現場に専任で配置されるため、兼務は難しいとされています。
ただ、どうしても人員不足で一人しかいないよ~といった場合には、例外的に兼任が認められる場合があります。
この例外が認められる場合が、
①工事現場への専任性が求められない工事であること
②専任技術者の所属する営業所が契約した工事であること
③専任技術者として適正に職務ができる範囲の近隣の工事現場であること
④所属する営業所と常時連絡がとれる状態であること
結論からいうと、公共性のある施設や多数の人が利用する施設に関する重要な建設工事では、専任の監理技術者または主任技術者を配置する必要があります。これらの工事では、専任技術者と配置技術者の兼務は原則として認められません。
公共工事に参加される場合は、きっちりと分けておく必要があります。大きな工事がせっかく取れたのに、厳しい指導が入ってなくなってしまったということもあります。
人員不足の折、どうにもままならないということももちろんあると思いますが、難しいところですね。
一方、工事の請負代金が一定額未満の場合や、工事現場間の移動時間や連絡方法などが一定の要件を満たす場合は、兼務が認められる場合があります。1時間以内くらいならすぐに戻れるからといった具合です。
これまでの感覚的には、一人親方や公共工事に参加されない業者様については、そこまで厳しくは見られていないようです。
建設業許可、経営事項審査のご相談もお気軽にお電話くださいませ。
水分補給中です
今日も暑さに負けないにゃ